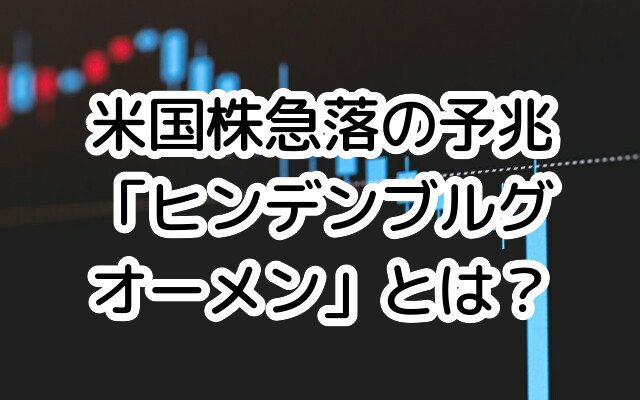
リーマンショック後、きれいな右肩上がりで上昇してきた米国株式。
2022年年初より、高値圏で不安定な相場が続いています。、2023年3月10日には、米国でシリコンバレー銀行が、12日にはシグネチャーバンクが破たんした影響で、欧米に金融不安が広がり、世界的に金融株が売り込まれました。また、大手銀行クレディ・スイスにもその影響が飛び火するなど、金融危機不安がぬぐい切れない状況です。
さて、このような金融危機の予兆を知るアラートの一つが、「ヒンデンブルグ・オーメン」です。
ヒンデンブルグ・オーメンは、米国の株価下落をよく当てることで知られる指標です。ちなみに、「オーメン(omen)」とは、英語で「よくないことが起こる前兆」のことを指します。
過去の点灯日は実際に米国株(S&P500, ダウ)の急落を言い当て来たのか?
本記事では、ヒンデンブルグ・オーメンの解説、及び、過去のアラート点灯日をチャートで確認することで、的中状況(的中率)を確認してみたいと思います。
目次
「ヒンデンブルグオーメン」とは?

ヒンデンブルグオーメンは、高値&安値銘柄数や移動平均線などを基に算出されるテクニカル指標です。ダウやS&P500など米国株式市場の株価暴落をよく示すとして知られています。
そのため、投資サイトなどでも、ヒンデンブルグオーメンが点灯すると、米国株の暴落アラート・株価暴落予測としてニュースでも話題になります。
アラート点灯「4つの条件]
ヒンデンブルグオーメンは、次の4条件を満たすと点灯します。また、点灯後、おおよそ1ヵ月ほどが下落警戒期間とされています。
- ニューヨーク証券取引所(NYSE)での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数がともにその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上
- NYSEインデックスの値が50営業日前を上回っている
- 短期的な騰勢を示すマクラレン・オシレーターの値がマイナス
- 52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない
暴落兆候のメカニズム:なぜ、株価暴落の兆しとなるのか?
では、なぜ、ヒンデンブルグ・オーメンが点渡欧すると、株価暴落のサインとなるのでしょうか?
通常、安全に機能している市場では、銘柄数と株価には以下の関係が成り立ちます。
最高値銘柄が多い時:最安値銘柄は少なく、株価は上昇
最安値銘柄が多い時:最高値銘柄は少なく、株価は下落
ヒンデンブルグオーメンが点灯している相場では、点灯の4条件の1つめにあるように「52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数がともにその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上」です。このような状態は、通常の相場とは異なる「異常な状態」であることを示しています。
ヒンデンブルグオーメン点灯で何が起こる?
では、ヒンデンブルグオーメン点灯すると、どのようなことが起こりやすいのでしょうか。
一般的に、以下の3つのいずれかが起こると言われています。
❶7%の確率でNYダウが5%以上下落
❷パニック売りになる確率41%
❸重大なクラッシュとなる可能性は24%
過去のヒンデンブルグオーメン点灯日を検証する(2018年~)
では、過去において、いつ、ヒンデンブルグオーメンが点灯し、その時、米国S&P500チャートの株価はどうなったのか見ていきましょう。
2018年~2021年に発生したヒンデンブルグオーメンの点灯開始日は以下のようになっています。
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1/19 2018/1/30 2018/4/24 2018/6/18 2018/7/18 2018/7/26 2018/8/2 2018/8/9 2018/9/5 2018/9/25 | 2019/5/10 2019/7/23 2019/8/2 2019/11/14 | 2020/1/28 | 2021/3/3~3/10 2021/3/24~4/1 2021/7/28 2021/8/18 2021/9/29 2021/11/18 2021/12/13 | 2022/1/11 2022/1/17 2022/2/14 2022/4/7 |
ヒンデンブルグオーメン点灯日をチャートで検証
上記チャートは、S&P500の日足と種脚のチャートです。ヒンデンブルグオーメンの的中率検証のため、チャート上に点灯日をでマーキングしています。
点灯から1ヵ月以内に下落となっていないものもありますが、大きなチャートの山谷はもちろん、相場の途中の小さな山谷(押し目)もかなり的確にとらえていることがわかります。
かなり高い的中率で暴落を言い当てているように思われます。的中率を過信することはできませんが、ヒンデンブルグオーメン点灯が点灯したら、損切を入れつつ売ってみると「暴落待ち投資」はありと思います。
米国3指数+日経平均+金利の連動性連動性
S&P500への暴落・下落アラートの点灯したとき、米国3指数はどう動いたのか?日足チャートで連動性を見ておきましょう。
・S&P500
・ダウ
・ナスダック
・日経平均
・米国債10年物金利
※2021年12月16日時点
S&P500 日足チャート
ダウ 日足チャート
ナスダック 日足チャート
日経平均 日足チャート
米国債10年物金利 日足チャート
皆さんご存知の通りですが、S&P500が下落すれば、米国株式3指数はに下落します。この際、3指数の動きには、米国債10年物金利とコロナ関連ニュース(直近では新種株の出現)が大きく関わっています。
以下では、ヒンデンブルグオーメンをふまえた長期戦略と超短期戦略について考えてみます。
ヒンデンブルグオーメン発生から考える長期戦略(直近数年)

2021年になって、明らかにヒンデンブルグオーメンの点灯頻度が上がっています。
今後、インフレと、それに対応したFRB政策の綱引きで、マーケットは不安定になる頻度が高まることが予想されます。ただし、個人的には、まだしばらくは上昇すると考えているので、安易に米国株式3指数に連動するポジションを手放さない方針です。むしろ、3口座で毎月自動積立でインデックス投信を買い増していますし、CFDでもどちらかというと積み増し状況にあります。
しかし、そろそろ、ポジションを減らしていく明確な基準・戦略を立てておかなければならないな、と考える次第です。
以下、過去の記事から、今後の戦略の参考になる記事を掲載してきます。
ヒンデンブルグオーメン発生時点(株価下落直前)に行う短期戦略

上述の通り、ヒンデンブルグオーメンの点灯頻度が上がる可能性があります。そして、点灯⇒下落の度に、iDeCo・積立NISAをはじめとする長期積立ポジションの値下がりにストレスを感じることになります。
せっかく、株価下落・暴落の兆候を事前に知ることができたとしても、それをヘッジする手段を持っていなければ意味がありません。
そこで利用したいのが、現物購入より少ない資金で下落ヘッジができるCFD口座。CFDなら以下のような投資戦略・戦術で資産目減りに対抗することができます。
- (利益が出ているポジションの一部を手仕舞う)
- CFDで米国株式3指数のいずれかを売る ※損切りラインの設定必須
- CFDで日経平均指数を売る
※米国3指数より、ビビットに反応する(うまくいけば、リターンが大きい) - VIX指数が下がりきったところで、暴落に備えてVIX指数を買っておく ※下落すればVIX指数は急騰する
毎回通用するとは限らないものの、戦う道具(口座や戦略)を用意しておかない限り、ヘッジはできません。暴落の備えとしても、準備をしておく価値はあります。
以下、記事は、上記を実施するに当たっての参考記事です。CFD口座を投資に活かす方法をまとめているのでご確認を!
【終了】ヒンデンブルグオーメンの確認方法(点灯状況)

残念ながら、ヒンデンブルグオーメン情報を配信してくれていたサービスは、終了してしまいました。非常に残念です。
【用語解説】マクラレン・オシレーター
マクラレン・オシレーターとは、マクラレン夫婦によって開発された「市場の騰落トレンド」を示す指標です。
マクラレン・オシレーター
= (Xの19日指数平滑移動平均) - (Xの39日指数平滑移動平均)
※X(騰落銘柄数) = (値上がり銘柄数) - (値下がり銘柄数)
※指数平滑移動平均:EMA (Exponential Moving Averageの略)
マクラレン・オシレータは、市況判断に以下のような分析に活かせます。
- プラスの時は市場が上昇傾向
- マイナスの時は市場が下落傾向
- 数値が±に極端に振れる際には「買われすぎ」「売られすぎ」の可能性があり
最後に
米国株急落の予兆「ヒンデンブルグオーメン」の意味と過去点灯日をチャート共に確認しました。
人は、人は暴落・下落時になかなか逃げれません。以下の記事もご確認を。
本記事が少しでもお役に立ったなら、記事を書く励みになりますので、 Twitterフォローや RSS(feedly)登録をしてもらえると嬉しいです。新規記事公開時にお知らせいたします。







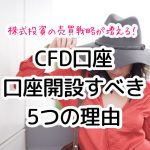






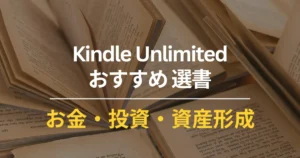


[…] ソース […]