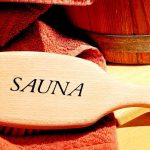最近、下町銭湯や、スーパー銭湯に行ったことありますか?
何年も行ったことがない人が多いと思うのですが、サウナ男子・サウナ女子にとっては、銭湯巡りはなかなか楽しい趣味です。私は、週6回程度サウナに行くサウナ女子。つい先日もおしゃれににニューあるした堀田湯に行ってきました。
温泉に行く時間とお金はない。そんな人も、銭湯に行くとちょっとした非日常が味わえる。少し足を延ばして遠征して、レトロ銭湯、おしゃれ銭湯+地元グルメを楽しめば、ちょっとした小旅行気分も味わえます。
今回は、最近の銭湯・サウナ事情と共に、銭湯&サウナの愉しみ方について紹介します。
目次
最近の銭湯・サウナ事情

廃業が続く、下町銭湯。今、東京に何軒銭湯があるかご存じですか?
銭湯最盛期は昭和40年代。17%まで減少
東京都の情報サイト東京くらしWEBによると、2022年12月末時点で、都内にある銭湯は462カ所。2021年では480件あったので、18件が廃業したことになります😭
東京の銭湯数は最盛期が昭和43年で2,687件。現在は2割を切り、17%になっています。これは全国的な傾向です。
最近のサウナ事情
新型コロナ感染で行動自粛が必要になった2020年。銭湯も大きく影響を受けました。
スーパー銭湯は営業を停止。一方、個人経営の銭湯は、公衆衛生を守るという観点から営業は継続されました。しかし、お客さんは激減。銭湯の廃業を加速させました。その後も、燃料価格の高騰など、厳しさは続いています。
2023年5月の段階ではお客さんは戻るものの、年配者の戻りは鈍く、一方、サウナの定着化などもあり、客層は大きく変わりました。
そのような中でも、多くの銭湯ファン、そして時代のニーズに合わせて施設を改装するなどの努力を重ねている銭湯もあり、そんな銭湯は、若いお客さんを取り込んでいます。
私はサウナーなので、どうしてもサウナ目線で銭湯を見てしまいますが、サウナが人気の銭湯は、同性の友達2~3人ずれで銭湯・スーパー銭湯を愉しんでいる人が多いです。もちろん、ぼっちサウナ派で、いろんなところに出向かれているのだろうなぁ、と思える方も、結構います。
以下の銭湯は下町銭湯で、そんなに駅からのアクセスがいいとは言えませんが、若い人も多いおしゃれ銭湯です。
銭湯の愉しみ方

私はサウナが好きで、少し足を延ばして銭湯に行ったりしますが、銭湯の愉しみ方はサウナだけではありません。
鉄道ファンに「乗り鉄」「撮り鉄」といったジャンルがあるように、銭湯ファンにも以下のようにいろいろなファンがいます。
・入浴そのものが好き
・サウナ大好き
・旅行・サ旅が好き
・建築学的な面白さに惹かれる
・昭和レトロが好き
何かこだわりを持って、銭湯に行くと、益々銭湯が楽しくなります。
私は、「サウナ✕旅好き」派
私の場合は「サウナ✕旅好き」と言ったところでしょうか。
私は観光地巡りが好きなので、完全「サ旅」はしたことがありませんが、泊まるホテルは「サウナ&大浴場があるホテル」と決めています。
サ旅に役立つ本は、以下の記事にて紹介しています。
サウナ効果を高めたり、サウナの時間を有効に利用するアイテムは以下にて紹介しています。
太陽光が入る昭和レトロ銭湯も最高
一方で、富士山の絵が描かれた昭和の雰囲気満載の銭湯も好き。このような銭湯は、天井が高く、昼間に行くと、日の光が入ります。
日中、太陽光でキラキラ✨光る湯面を見ながら、リラックスしながら入る銭湯は最高です。
昭和レトロを感じながら、昔を懐かしんだり、ゆったりと流れる時間を楽しんだりしていると、心身がほぐれ、日常で貯まった体のこわばり、頭のモヤモヤも解放されていきます。
500円程度で、小旅行に来たような気持ちも味わえ、とても贅沢な気分になれますよ。
入浴料金の変遷

サウナや温泉に行くと、「入浴料」を支払う必要があります。
昭和21年以降、銭湯の入浴料金は物価統制令に基づき都道府県ごとに定められています。
東京都は500円
東京都の入浴料金統制額は大人500円(2021年7月15日~)。
東京都では知事から諮問を受け、学識経験者、利用代表者、業界代表者、関係行政機関から構成される「東京都公衆浴場対策協議会」が料金を検討しその意見をもとに決定されています。
利用者の負担を軽減するため原価計算された料金よりも低く設定されています。
料金は以下のように徐々に高くなってきています。でも、昨今の食料品・日用品の上昇に比べると、明らかに価格が抑えられています。
| 施行年月日 | 大人 [12才以上] | 中人 [6才以上12才未満(小学生)] | 小人 [6才未満(未就学児)] |
|---|---|---|---|
| 2000年5月21日 | 400円 | 180円 | 80円 |
| 2006年6月1日 | 430円 | 180円 | 80円 |
| 2014年7月1日 | 460円 | 180円 | 80円 |
| 2019年10月1日 | 470円 | 180円 | 80円 |
| 2021年8月1日 | 480円 | 180円 | 80円 |
| 2022年7~8月 | 500円 | 180円 | 80円 |
銭湯 VS ジム、どっちが安い
私は、普段はジムで入浴&サウナをしています。
そこで、銭湯 VS ジム、どっちがお得か、シミュレーションした結果を以下の記事にて紹介しています。
なお、私は、自宅でお風呂&シャワーを使う回数が極めて少ない+キッチンもIHなので、べらぼうにガス代が安いです。過去2年では1000円を下回ったこともありました。この辺あたりも考えると、ジムは極めてコスパよしです。
最後に
今回は、最近の銭湯・サウナ事情と共に、銭湯&サウナの愉しみ方について紹介しました。
銭湯巡りは結構楽しいです。まずは、お近くの銭湯から、楽しんでみてはいかがでしょうか。