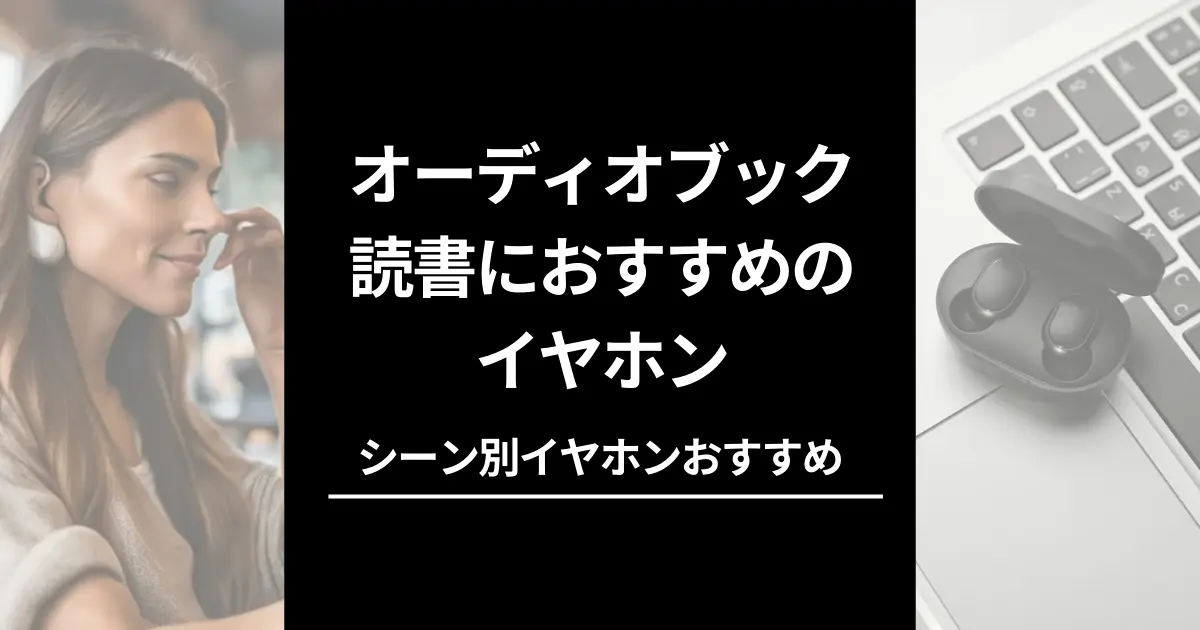古典名著などを読むと思うことがあります。「人間って、古代から変わっていないなぁ…」と。
古代人も現代人も、個人的な悩みは大差ありませんし、お金や名誉を求めます。また、個人の枠を超えて、社会という枠組みから見ても、戦争はするべきでないとわかっていても、未だになくなることはありません。
科学技術は猛烈なスピードで進歩していますが、人間の「心」は成長していません。それは「人間の本質」、すなわち「人間の本性」そのものが、ずっと変化していないからなのかもしれません。
本書「人間の本性」の著者 伊藤忠商事の社長・会長を務めた丹羽宇一郎さんは、科学技術の深化と人間の心の成長の落差が、至るところでいま、大きな問題となって表れていると指摘します。
人間として生まれたのに、肝心な人間のことをよく知らなければ、これからのAIやロボットに使われる一方で、人間としての人生そのものさえ、まっとうできなくなってしまいます。
そこで、今回は、著書「人間の本性」から、そんな人間といかに付き合い方、生きる方を学びます。
目次
「動物の血」と「理性の血」

人間が生物界の頂点にいるのは、脳が極端に発達して理性という道具を手にしたからです。ただ、人間は所詮、動物です。飢え死にしそうになったら、人の命を奪ってでも食べ物を得ようとする本能を持っています。丹羽さんはこれを「動物の血」と呼んでいます。
いかに、「動物の血」をコントロールできるかが大事
「動物の血」は、怒り、憎しみ、暴力的な衝動を内包します。しかし、人類誕生以来、人間は「動物の血」をうまくコントロールすることができません。だから、油断をすると、人間のなかに潜む「動物の血」が騒ぎ始めてしまう。それ故、長きにわたって同じ過ちを繰り返しています。
生物進化の歴史を辿れば、生命が誕生したのが38億年前、人類の直接の祖先で新人類が誕生したのが約20万年前、そして最古の文明が生まれたのが4000年~1万年前といわれています。つまり、「動物の血」のほうが「理性の血」に比べれば歴史が圧倒的に長く、それゆえ強靭です。
「理性の血」の底には「動物の血」が流れている。まずは、このことを認識しなければなりません。
人間の善悪
いわゆる善悪というのは、「理性の血」が「動物の血」をコントロールできている状態が「善」、「理性の血」が姿を消し、「動物の血」が噴き出す状態が「悪」といってもいいと丹羽さんは指摘します。
ですから、世の中には善だけでできている善人もいなければ、悪だけの悪人もいません。
「動物の血」が姿を現すには努力は必要ありません。しかし、理性の力によって自らをコントロールするには努力が必要です。ときにより善になったり、悪になったりする二面性をどうコントロールできるかがカギとなります。
「利他の精神」がなければ「人間」じゃない
私たちの大半は、自己中心主義です。
しかし、人間という字は人と間と書くように、人との交わりがあったり、他人を意識することで「私」という自意識が生まれ、人間になります。人は他者を意識したり、交わったりすることで向上心を抱いたり、努力をしたり、喜びを感じたりできます。だからこそ、「利他の精神」は必要です。
人生の勝敗は最後に決まる
人は勝ち負けといったことに、とてもこだわります。この競争社会に生きていると、勉強の勝ち負けから仕事の勝ち負けまで、勝つことにこそ生きる価値があると思っている人も少なくありません。仕事で成功してお金持ちになれば人生の勝ち組ような価値観も根強くあります。
しかし、人生の本当の勝ち負けは、仕事でうまくいくとか、お金持ちになるとかなどの物差しだけではかれるものではありません。それはおそらく人生最後の心安らかな 安堵 の一息に象徴されることだと丹羽さんは指摘します。
では、どうしたら、最後を幸福にできるのか。まずは、「最後」を意識しましょう。すると、今日が変わるはずです。
運と生き方

「あの人はいつも運がいいな」と周囲から思われている人がいます。当然、努力もそれなりにされていますが、それ以上に運に恵まれている。このような人は何ゆえにそうなるのでしょうか。
「運」は偶然ではない
私たちは「運」というと、どこか神がかり的で偶然の要素が高いものと考えます。確かに、宝くじのように全く偶然の運もあります。しかし、多くは、因果応報といわれるように、しかるべき努力や準備をしてきたからこそ恵まれる「必然の運」が大半です。私たちが運がよかった、悪かったなどといっている多くは、実はこの「必然的な運」です。
「運」を引き寄せる努力の仕方
では、「しかるべき努力・準備」はどのようにして進めたらいいのか?
ビジネスでは、成功の確率を高めるために市場を研究調査して分析するという努力が必須です。運についても同じ。「偶然の要素」を減らして、必然の運に恵まれるように、努力の仕方も考える必要があります。
人間としての「幸せ」の構造

幸せに生きるためには、人間はどのように生きると幸せなのかを理解する必要があります。
目先の小さな損得にとらわれすぎない
損か得かという判断は、人間が行動する際の重要な基準となります。特に、経済至上主義の世の中においてはそうです。
しかし、何が損で何が得かという結論は、目先の計算だけではわからないことが実に多い。「損して得とれ」「急がば回れ」というように、一見そうな行動がまわりまわってとくとなることはよくあります。だからこそ、目先の小さな損得にとらわれすぎる行動はよくありません。
気持ちのいい生き方をしているか
損得勘定ばかりの生き方から離れるためには、楽しいかつまらないか、面白いか面白くないか、あるいは気持ちがいいかそうでないかを考えてみるといいです。気持ちがいいと思う価値観で行動を起こすようにすれば、損得勘定だけの窮屈な人生からは解放され、心豊かな日々を過ごせます。
気持ちよく生きられる人こそ最終的には最も「心豊かな人生」が送れます。
足るを知るものは富む
上記のような生き方をするには「足るを知る」ことが大事です。
ここで大事なのは、自分は本当のところ何を望み、何を求めているのか、どういう状態であれば心は本当に満たされるかなど、自分をよく知らなくては「足るを知る」ことはできません。
他人と比べることで優劣を感じるのではなく、本心から自分が望むこと、やりたいことを見つめる。そうすれば人と比べることもなくなり幸せになります。
人間は生きているだけで幸せなことになかなか気がつけません。命がなければ何もできません。この世に「生」をうけ存在していることがとてもありがたいことだと知ることです。足りないものを数えるのではなく、あるものを再発見して感じ味わう。そんな視点から自分を今一度見つめ直すと、「足るを知る者は富む」の心境に近づけるのではないかといわさんは指摘します。
本書からの私の最も大きな気づき:なぜ読書するのか

私は、本書から得た最も大きな学びは、まぜ、私は読書が好きなのか、読書をし続けるかに対する一つの答えがあったことです。
「読書」と「人間の本性」。一見、何のつながりもないように見えますが、どういうことでしょうか。
知的好奇心が最終的に行きつく先
私が読書をする理由は、とにかく楽しいから。ワクワクする好奇心が増すからです。
読書をすればするほど、「こんなことがあるのか!」と思い、もっといろいろなことを知りたくなる。一向に好奇心の種が尽きることがありません。丹羽さんも同じ考えをお持ちで、贅沢はしない代わりに読書だけは贅沢すると(別の本で)語るほどの読書家です。
そんな、丹羽さん曰く、そんな知的好奇心が最終的に行きつく先は、「人間とは何者なのか」という根源的な問いではないかということ。
確かにその通りかもしれません。世の中の真理はもちろんですが、自分が幸せに生きてくためにも、自分(人間)とは何者なのかを探求し続けていると言えるかもしれません。
人間が幸せに生きるために必要なこと
「人間とは何か」を知るのは、自分が幸せに生きるためです。そして、この類の本を読んでいると、かなり高い割合で、ある教えにたどり着きます。
その教えとは、「清く、正しく、美しく生きなさい」ということです。
本書では、指導者が必要な倫理として、教育者である 新渡戸稲造 が著した『武士道』を例に説明していますが、武士道精神の源にあるの仏教・神道・儒教の教えの内、「儒教」で人が常に守るべき5つの道徳「仁・義・礼・智・信」は、簡単に言えば、 「清く、正しく、美しい生き方」です。
利己心を抑えて人を思いやる「仁」
筋を通し正しいことを行う「義」
人間関係を円滑に進めるための社会秩序である「礼」
道理をわきまえ正しい判断を下す能力である「智」
偽らず、欺かず、人の信用を得る「信」
いずれも「清く、正しく、美しく」を実践することと同じです。これらは、充実、かつ、幸せな人生を送るために欠かせません。
最後に
今回は、丹羽宇一郎さんの「人間の本性」について紹介しました。
本文冒頭でも書いた通り、人間として生まれたのに、肝心な人間のことをよく知らなければ、これからのAIやロボットに使われる一方で、人間としての人生そのもを、幸せに全うすることは困難です。「武士道」を再読し、「清く、正しく、美しく生きる」ことについても、改めて、再認識したいと思いました。
丹羽さんの体験談も多く、サラサラ読み進められる本ですので、是非、お手に取って読んでみられることをお勧めします。