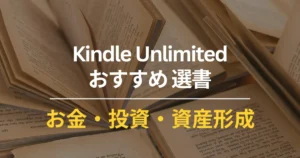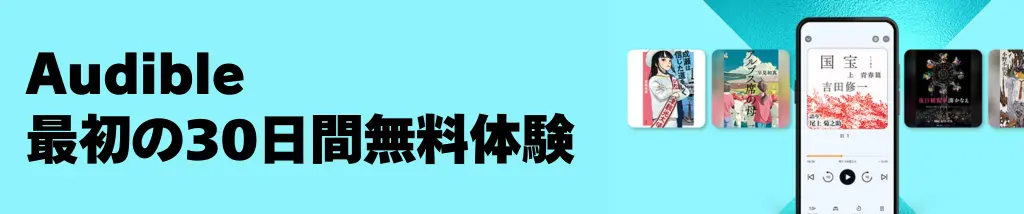新NISAの陰で見過ごされがちなiDeCo(個人型確定拠出年金)。
しかし、一部の人は『積み立てる時:掛金が「全額所得控除」』『運用期間中:運用益が「非課税」』『受け取る時:受け取り方に応じて「税制優遇」』という3台メリットを活かして、将来の資産形成の柱としている制度でもあります。
そのiDeCoが、2025年の年金制度改革法の成立(2025年6月13日 成立)によって大きく進化しようとしています。
iDeCoは今後どう変わるのか――。
最新の制度変更ポイントと、iDeCoの活用メリットと注意点、出口戦略を考える上での重要ことをまとめておきます。
目次
iDeCoはこれからどう変わる?最新制度改正【まとめ】

✅ 加入できる年齢が【65歳未満 → 70歳未満】に延長予定
・働き方が多様化する中、「70歳まで働く=70歳まで積み立てられる」時代に。
・定年後も資産形成の選択肢が広がる
✅ 掛金の上限が大幅アップ!もっと積み立てできるように
| 対象者 | 現在の上限(月額) | 改正後の上限(予定) |
|---|---|---|
| 自営業(第1号) | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 企業年金なし会社員 | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 企業年金あり会社員・公務員 | 1.2〜2.0万円 | 企業型DCと合わせて6.2万円まで可能に |
・積立額を増やせる=節税効果UP!
・会社員・公務員でも「がっつり積み立て」できる時代に。
✅ 企業型DCとの併用ルールが大幅に緩和
・これまで「iDeCoをやると企業型DCが減る」などの制限 → 今後は併用がしやすく
✅ 退職金との受け取り時期に要注意「10年ルール」へ【重要】 ※後述
・iDeCoと退職金を同時期に受け取ると控除枠が減って税金が増えることも…。
・今後は受け取り時期の間隔が10年以上ないと非課税枠が分けられない(2026年施行予定)。
こんな人にメリットあり!
🟡 既に満額の掛け金をかけてきた人
→上限アップで控除枠が増える。節税効果UP!
🟡 60歳すぎても働く人
→70歳未満まで加入可能になれば、資産形成を長く続けられる。
🟡 企業年金があるけどiDeCoも使いたい人
→併用がしやすくなり、ライフプランに合わせた自由な積立が可能に!
今後のiDeCo利用における注意点は?

見逃してはいけないのは、受け取り方を間違えると税金が増えるケースがある点です。
なぜiDeCoの受け取り方で税金が増えるのか?
iDeCoの受け取りには、以下の2通りの方法があります:
| 受け取り方法 | 税務上の扱い | 主な控除 |
|---|---|---|
| 一時金として受け取る | 「退職所得」扱い | 退職所得控除 |
| 年金として受け取る | 「雑所得」扱い | 公的年金等控除(65歳未満:最低60万円) |
問題になるのは、「一時金」として受け取るときの退職所得控除の重複・圧縮です。
✅【参考】退職金控除は勤続年数により決まる
・20年以下の場合 → 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・20年超の場合 → 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
例)勤続30年なら → 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円まで非課税!
こんなケースで税金が増える
退職金とiDeCo一時金は、同じ「退職所得控除枠」を使うため、受け取りのタイミングによっては、控除額が減って課税対象になってしまうことがあります。
✅ 税金が増える例
・60歳で退職(退職金を一括で受け取る)
・61歳でiDeCoを一時金として受け取る
→ この場合、iDeCoは退職金と同じ控除枠を使ってしまう
→ 非課税枠がほとんど残っておらず課税される可能性が
【2026年から新ルール】10年ルールに要注意
2026年施行の改正で、以下のようなルールが導入されます。
・同じ退職所得控除枠を使う2つの所得(例:退職金とiDeCo一時金)を、
・「10年以上の間隔」をあけて受け取らないと、非課税枠が分離されない。
iDeCoのメリットの裏で、しれっと仕込まれた「改悪」で、期間が5年→10年に変更されました。
【最大限に活かす方法】税金を抑える3つの戦略
🔴 受け取りタイミングを退職金と10年以上ずらす
・退職金を60歳で受け取ったら、iDeCo一時金は70歳以降にする。
・これにより退職所得控除が個別に適用され、両方とも大部分が非課税になる。
🔴 年金方式で分割受け取りにする(雑所得控除活用)
・一時金ではなく、5年〜20年の分割受け取り(年金方式)にすると、
・雑所得扱い+公的年金等控除が適用され、所得税が抑えられる。
・特に年収が少ない年(退職後)に分けて受け取ると税率が下がる。
🔴 退職金を分割で受け取るか、企業側と調整する
・大企業の場合、退職金を「分割退職金」として複数年に分けて支給できるケースもある。
・税負担が一度に集中しないよう、企業型DCや退職金との連携も大事。
✅実際の取り崩しイメージ
退職金の額や、積立額などによって状況は異なりますが、効果的な制度利用の雰囲気が伝われば!
| パターン | 退職金 | iDeCo | 結果 |
|---|---|---|---|
| ❌同じ年に一括受け取り | 2,000万円 | 500万円 | 控除枠を超え、iDeCoに課税発生 |
| 退職金後に10年以上 あけて受け取り | 2,000万円 | 500万円 | 両方非課税に近いかも |
| iDeCoを20年分割で 年金受け取り | 2,000万円 | 年25万円×20年 | 年収が低い年なら税負担軽微 |
私の場合
私の場合、退職金とのiDeCo資金受取の控除枠のカニバリを心配する必要はありません。
ただし、毎月6.8万円を積み立てています。今後、7.5万円まで積立を引き上げれば、iDeCo受取のころには、そこそこの資産額となり、受け取り時の税金問題が浮上します。
目下、グローバルな株高もあり、資産額が1,000万円を超えてきました。さらに、入金投資は続くので、上下動しながらも、右肩上がりに増えることになります。(仮に今後10年継続するなら、積立原資だけで、7.5万円×12カ月✕10万円=900万円が増加)
会社員の方も、改正後は、月の積立上限が大幅増えるので、上限いっぱい積み立てれば、iDeCo受取時は大きな資産となります。
ちょっと、今の段階では、5年先すら見えないので、明確な出口戦略は見えません。
60歳に近づいてきたら、どのタイミングで、どのように、受け取りを開始するか?
他の資産状況、自分の健康状況、就労状況を鑑みて、最も効果的な受け取り方法を再考する必要があります。
✍️ まとめ:iDeCoは「積極的に使う時代」へ!
制度が「使いにくい」と敬遠されてきたiDeCo。
しかし、「使いこなせば超お得」へと進化するiDeCo。
節税しながら、長期で資産形成できるこの制度を活かさない手はありません。
「人生設計の柱となるiDeCo」へ――
まだ利用していない方は、資産設計戦略を再考する価値は十分あるかと。
😞とは言っても、新NISAの年間非課税投資枠も増え、さらにインフレも手伝って、家計はそれどころじゃないという方も多いのが、今の日本の実態かもですが…