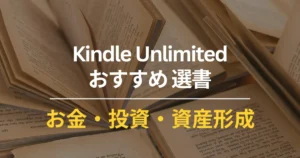高市早苗・新総裁誕生:「積極財政」への期待が市場を席巻
2025年10月4日に行われた自民党総裁選で、高市早苗氏が新総裁に選出されました。
このニュースを受け、金融市場では高市氏が掲げてきた「積極的な財政政策」への期待感が一気に高まり、週明けの日経平均は前週末比で2,000円超の急騰。市場はまさに「期待先行」で沸いています。
高市氏はこれまで一貫して、財政出動による景気刺激策を重視してきました。
今後の日本経済を考える上で、高市新総裁の政策スタンス「サナエノミスク」とその影響(期待とリスク)を確認しておきます。
目次
株式市場の反応:日経平均が史上初の4万7000円台へ
日経平均:日足
総裁選結果の報道を受け、東京株式市場では買いが殺到。
10月6日の取引では、日経平均株価が一時2,000円以上上昇し、史上初の4万7,000円台を突破しました。
📌石破首相の退陣表明(9月5日)以降、わずか1か月で約2,700円の上昇を記録。
👉まさに「政権交代=相場転換」という図式
日経平均:長期チャート2003年~
📌昨今の値動きの激しさが伺える
【サナエノミスク】高市早苗氏の政策スタンス:「責任ある積極財政」
高市氏の経済政策は、「緊縮からの転換」を鮮明に打ち出しています。
これまでの、石破政権の路線とは異なります。
以下のような方針が特徴的です:
✅ 「責任ある積極財政」
無制限のバラマキではなく、成長投資と財政健全化を両立させる方針。
必要な分野には大胆に資金を投入する姿勢を示す。
✅ 成長分野への重点投資
AI、半導体、バイオ、先端医療、防衛・安全保障といった成長領域へ選択的に投資。
→ 国の成長エンジンを再構築する狙い。
✅ 赤字国債を否定しない現実路線
金利引き上げに反対、金融緩和継続。
財源確保のために、赤字国債発行も「やむを得ない選択肢」と発言。
「金融政策の方向は政府が決め、日銀が支える」との考えを示し、財政と金融の連携を強調。
期待と課題が交錯:「積極財政」で何が変わる?
高市政権下で「積極財政」が実行に移された場合、想定される影響は多岐にわたります。
1️⃣ 成長分野の加速と企業価値の押し上げ
政府主導の投資拡大により、AIや半導体などの関連銘柄が上昇。
日本の産業競争力回復への期待が広がる。→株価は実際に上昇中
2️⃣ 内需刺激と雇用創出
インフラ整備、地方創生、社会保障改善、子育て・教育支援、医療・介護の強化など支出拡大は、消費と雇用を下支え。
→ 実体経済に直接効果が及ぶ可能性(消費や雇用を下支え)
3️⃣ インフレ圧力の高まり
支出拡大が行き過ぎれば、物価上昇を加速させる懸念。
→ 特に供給側の制約が強い分野では、国民負担増につながるリスクも。
4️⃣ 金利上昇と財政悪化リスク
国債発行増 → 長期金利上昇 → 利払い負担拡大の悪循環も。
→ 市場が政府の信用を疑えば、国債利回り上昇にもつながりかねない。
5️⃣ 市場の期待変化・リスクプレミアム
政策期待で株式市場は急騰
→実行力・持続性への懐疑が高まると、期待の剥落によって逆回転リスク
6️⃣ 為替動向:円安圧力の強まり
拡張財政と金利上昇見通しで円安基調が継続。
一方で、輸出産業には追い風となる側面も。
→ プラスとでるか、マイナスとでるか?
ドル円:日足
📌ドル円は一気に159円手前まで上昇
政策実現への壁:制度・調整・信頼性
期待が高まる一方で、実行面では次のような課題が立ちはだかります。
✅ 硬直的な予算制度:縦割り行政のため、迅速な政策転換が困難
✅ 与野党調整の難航:公明党や野党との協議が避けられず、政策後退の可能性
✅ 財務省とのせめぎ合い:財政規律を重視する財務省との調整が最大の焦点
✅ 市場の信頼性リスク:国債増発で格付け低下・金利上昇を招く恐れ
✅ 出口戦略の欠如:拡張政策をどの時点で縮小に転じるか不透明
✅ インフレと供給制約の衝突:需要刺激だけが進めば実質所得を圧迫しかねない
総括:本格化するか、それとも期待で終わるのか
高市新総裁の誕生は、市場にとって「積極財政復活」の象徴として歓迎されています。
しかし、実行には政治的・制度的ハードルが山積しています。
• 財政拡大に伴う 長期金利の上昇、円安の進行、インフレ加速 への警戒
•「責任ある積極財政」と掲げながらも、支出が膨張し続ける 制御不能リスク
• 組閣・予算編成・与野党調整・財務省との関係など、政策実現の不確実性
結局のところ、「積極財政」が本当に機能するかどうかは、単なるスローガンにとどめず、政策間の高度な調整力、そして、説明責任・透明性の確保にかかっています。
巨額の債務を抱える日本において、債務拡大・金利上昇・為替変動・物価上昇 といったリスクをどうコントロールしていくのか――。
日本が本当に“成長と安定”を両立できるのか、今後の展開に注目していきたいと思います。